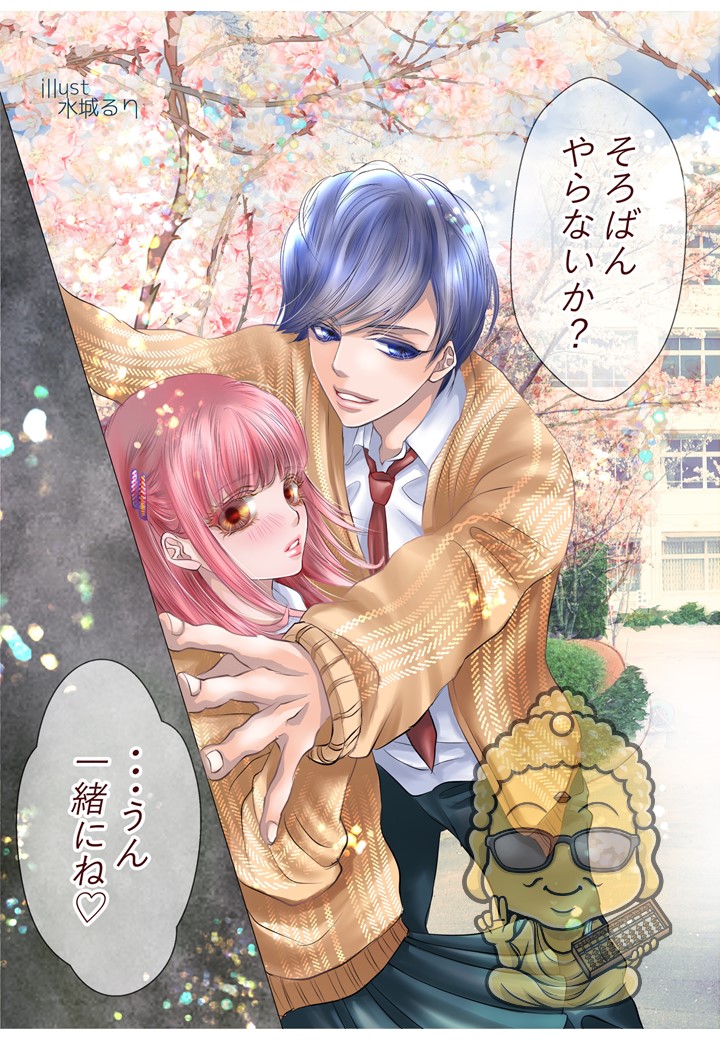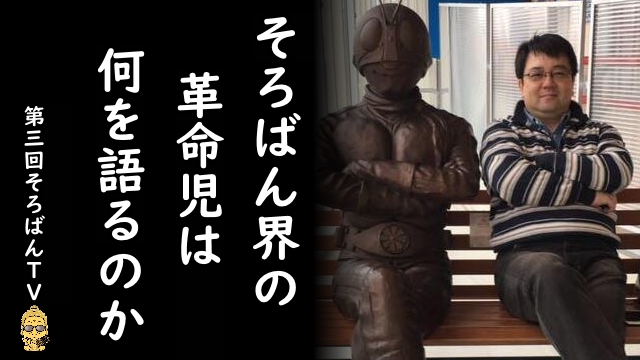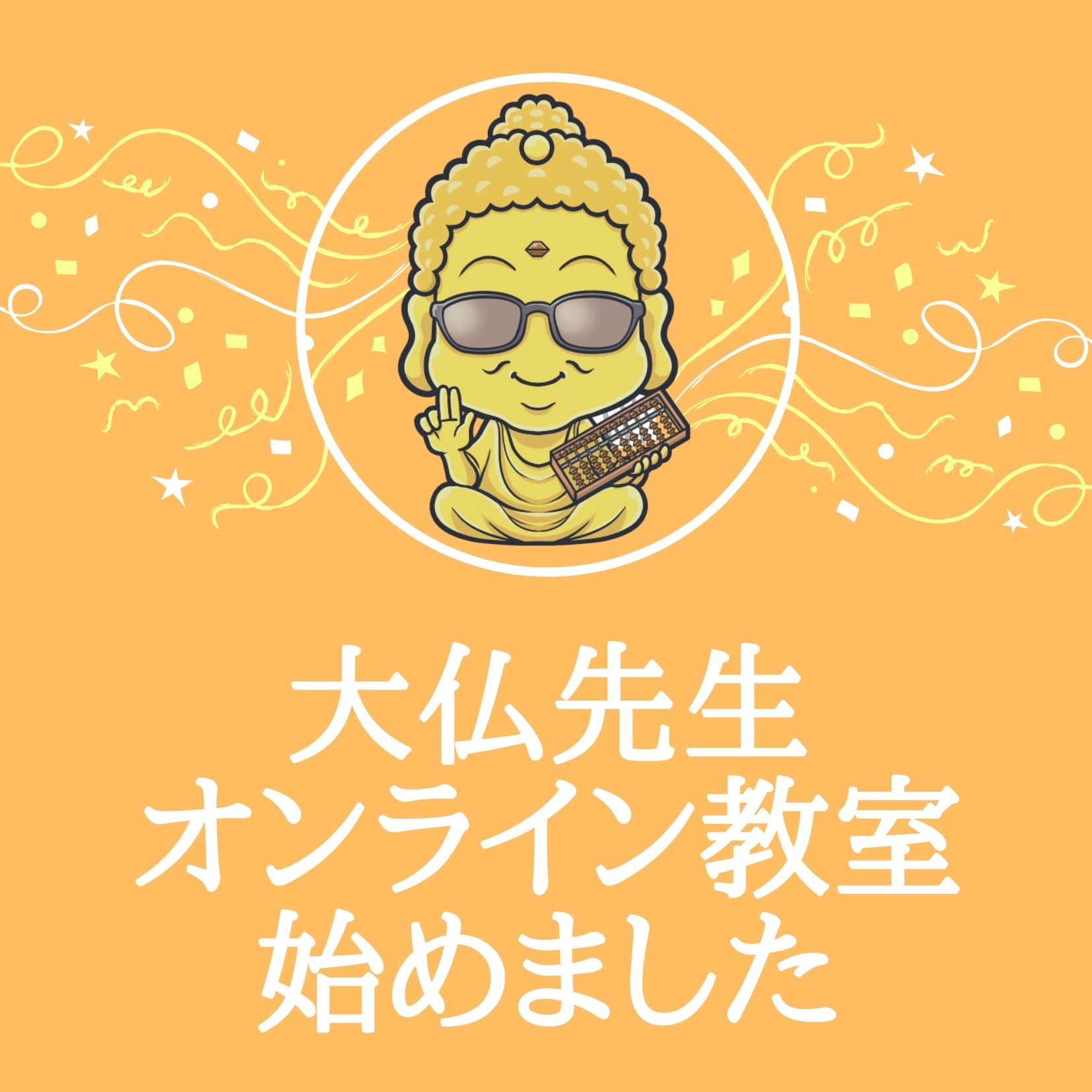長い間、子供達に習わせたいお稽古として人気のある「そろばん」。
現在も多くの子供達がそろばん教室に通って、日々学んでいます。
そろばん玉をはじくのは、子供達にとってはとても楽しい事のようです。
しかし、楽しい事ばかりではありません。
少しずつ問題が難しくなり、簡単に解けない問題も出てきます。
最初にぶつかる問題は、『繰り上がり繰り下がり』ではないでしょうか。
今回は、『10の繰り上がり繰り下がり』の教え方を説明いたします。
そろばんの教え方【補数】

5の繰り上がりを覚えたら、次は10の繰り上がりの練習です。
10の繰り上がりの練習をする時に、覚えておいて欲しいのは”補数”という言葉です。
補数とは、「ある数にたいしていくら足りないのか」を示す言葉です。
そろばんのたし算を覚えるためには、必ず補数を覚えておく必要があります。
10の補数を覚えよう
10の繰り上がりを覚えるには、10の補数を完璧に覚えておきましょう。
例えば8の補数はいくつですか?
8を10にするために足りない数は、2ですよね。
これが補数です。
9の補数は1
8の補数は2
7の補数は3
6の補数は4
5の補数は5
4の補数は6
3の補数は7
2の補数は8
1の補数は9
これなら簡単に補数を覚えられますね。
そろばんを始めたばかりの子供達は、まず補数を覚えましょう。
補数を覚えられない時は指を使おう
幼稚園・保育園、小学校低学年の子供達には、補数を覚える事は難しいかもしれません。
しかし、子供達自身の両手の指を使い、補数を考えさせると意外にすぐ覚えてくれます。
指を2本曲げると、伸ばしたままの指は8本
指を4本曲げると、伸ばしたままの指は6本
曲げた指と、伸ばした指の数が、その数と10の補数となります。
幼い子供達に教えるときは、補数という言葉は使用せずに、「お友達の数」など分かりやすい教え方にしましょう。
「8のお友達は?」「2」
「7のお友達は?」「3」
「6のお友達は?」「4」
「5のお友達は?」「5」
このような教え方で、補数を覚えてもらいましょう。
補数を覚えたところで、補数を使って繰り上がりの足し算をやってみましょう。
そろばんの教え方【10の繰り上がり】
10の繰り上がりは、こちらの動画がオススメです。
1つずつ動画をしっかり見て覚えましょう。
補数を覚えたら、実際に色々な数をたし算してみましょう。
まず分かりやすいたし算として、9のたし算をしてみましょう。
9をたす場合には、5円玉と1円玉4つ、一つの桁すべての珠をたす必要があります。
9をたす計算は、すべて10の繰り上がりを使う必要があります。
そろばんでは、9以上の珠を置くことが出来ませんからね。
足せない時に、10の繰り上がりを使って計算します。
足せなくなった時に、先ほど覚えた「お友達の数(補数)」を使います。
9のお友達は1なので、一の位から1を取ってから十に繰り上がる。
十に繰り上がるとは、一つ左の十の桁に1をいれることです。
9をたす時は、1を取って10をたす
8をたす時は、2を取って10をたす
7をたす時は、3を取って10をたす
6をたす時は、4を取って10をたす
5をたす時は、5を取って10をたす
4をたす時は、6を取って10をたす
3をたす時は、7を取って10をたす
2をたす時は、8を取って10をたす
1をたす時は、9を取って10をたす
お友達をとって十に繰り上がる。
ひたすら10の繰り上がりの練習を繰り返して、頭で考えなくても計算できるようになりましょう。
10の繰り上がり(上級編)
10の繰り上がりがもう完璧だよ!!という方に、もう少し早く計算できる方法を教えます。
10の繰り上がりの中でも
- 1をたす時
- 2をたす時
- 3をたす時
- 4をたす時
時に、少し工夫をするだけで繰り上がりの計算が早くなります。
例えば
1をたす時、9をとって10をたすので
- 1の珠を4つとる
- それから、5の珠をとる
- そして10に珠を入れる
これが一連の流れとなります。
この動作が完璧な方は、
1たす時は9をとって10をたすので
- 一気に1の珠4つと、5の珠をとる
- 10に球を入れる
2つの動作で10の繰り上がりが出来るようになりました。
このように、そろばんをはじく回数を減らしていくことで、問題を解くスピードが上がっていきます。
1をたす時と同様に
2をたす時は一気に8をとる
3をたす時は一気に7をとる
4をたす時は一気に6をとる
このように、短縮した10の繰り上がりも覚えるようにしましょう。
そろばんの教え方【10の繰り下がり】
10の繰り上がりを覚えたら、次は10の繰り下がりです。
10の繰り上がりの時には、「一の位の補数を取って10に繰り上がる」を覚えたので、10の繰り下がりは逆のことをします。
「10を取って、一の位に補数をたす」
これが10の繰り下がりの基本です。
1を引く時は、10を取って9を足す
2を引く時は、10を取って8を足す
3を引く時は、10を取って7を足す
4を引く時は、10を取って6を足す
5を引く時は、10を取って5を足す
6を引く時は、10を取って4を足す
7を引く時は、10を取って3を足す
8を引く時は、10を取って2を足す
9を引く時は、10を取って1を足す
繰り上がりの逆を覚えれば、10の繰り下がりも簡単ですよ。
10の繰り下がり 注意点
10の繰り下がりで難しい点があります。
- 6ひく時
- 7ひく時
- 8ひく時
- 9ひく時
この4つの場合は注意が必要です。
『6をひく時は、10とって4をたす』となりますが、もう一つ『10とって5をたして1をひく』というやり方もあります。
1の位に4を出せない場合は、まず5をとってから1をたします。
こちらの方が使用する回数が多いので、しっかりと覚えましょう。
- 6をひく時は、10とって5をたして1をひく
- 7をひく時は、10とって5をたして2をひく
- 8をひく時は、10とって5をたして3をひく
- 9をひく時は、10とって5をたして4をひく
ここまで覚えれば、10の繰り上がりのプロになれます。
何度も何度も繰り返し練習をしましょう。
そろばんは繰り返し練習が大切

繰り上がり繰り下がりは、そろばんを始めて最初にぶつかる壁ですが、やり方がわかれば簡単ですよね。
補数を覚えながら何度も練習し、頭で考えなくても勝手に補数が出てくるくらいまでそろばんをはじきましょう。
繰り上がり繰り下がりは、そろばんの基本です。
これをマスターすれば、そろばんがもっと楽しくなりますよ。
こちらの記事も参考にしてください。